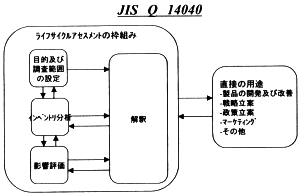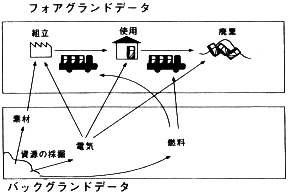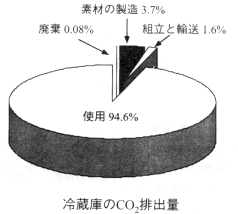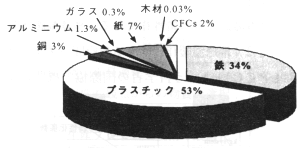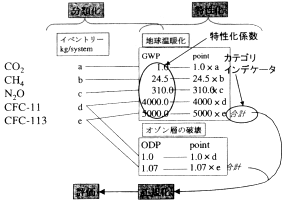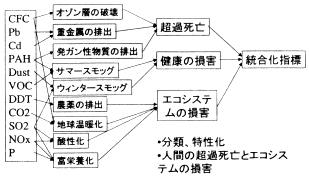| 論 文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境を考慮した製品設計・製造技術 −ライフサイクルアセスメントをめぐって−
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稲 葉 敦 (通産省 工業技術院 資源環境技術総合研究所 企画室長)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. はじめに | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このように、 「環境を考慮する」 ことの重要性は強く認識されるようになったが、 その製品がどのように環境に影響を与えているのか、 きちんと評価することはまだほとんど行われていない。 たとえば、 現在の家電製品を 「環境にやさしく」 するためには、 家庭で使っている間の消費電力を少なくすることや、 製品に使用されている鉄やプラスチックなどの素材の使用量を少なくすることが思い浮かぶ。 しかし、 そうすることによって、 環境への影響をどれだけ減少させることができるか、 評価した例はほとんどない。 素材の使用量と消費電力の削減のどちらを優先することが 「環境へやさしい」 ことになるのか判断するためには、 家電製品のことだけではなく、 発電や素材の製造時の 「環境への影響」 を考察することが必要になる。 たとえば、 石炭を使う火力発電所では、 電気を作るために石炭を燃焼させる。 その時に二酸化炭素 (CO2 ) が大気中に排出される。 鉄やプラスチックを作るときにも、 熱や電気のエネルギーが必要とされ、 それを供給するために石炭や石油などが燃焼され、 二酸化炭素が排出される。 大気に排出された二酸化炭素は 「地球温暖化」 の原因となる。 「地球温暖化」 を抑制するためには、 二酸化炭素の排出量を少なくすることが必要である。 したがって、 「地球温暖化」 の防止に役にたつ 「地球にやさしい」 家電製品に改良するためには、 家電製品を使っている間に消費する電気の量を発電所で発電する時に出される二酸化炭素の量に換算し、 一方、 家電製品に使われている素材の量をそれを生産する時に出される二酸化炭素の量に換算して、 比較して見ることになる。 発電所で燃焼される石炭や、 鉄の原料となる鉄鉱石を採掘する時にも、 採掘機械やトラックが使われ、 それらの燃料の消費により二酸化炭素が排出される。 さらに、 家電製品を廃棄する時にもその処分のためにエネルギーが使われ、 二酸化炭素が排出される。 したがって、 家電製品が生産され廃棄されるまでに関係するさまざまな過程での二酸化炭素の排出量を計算することが必要になる。 家電製品を生産するための資源の採掘 (ゆりかご) から廃棄 (墓場) までの一生 (ライフサイクル) に関係する分析 (アセスメント) を行うこと (ライフサイクルアセスメント) が必要となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. ライフサイクルアセスメント
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCAは、 製品やサービスの生産から廃棄まで (ライフサイクル) の物質とエネルギーの流れにそって、 環境への排出物量や資源の消費量を一貫して計量し、 環境への影響を評価する手法である。 LCAの手法については、 すでに1997年6月にその 「原則および枠組み」 を示す国際標準規格(ISO-14040)が発行されている。 また同年11月に日本工業規格(JIS-Q-14040)となっている1)。 そこでは、 LCAを 「サービスを含む製品に付随して生じる影響をより良く理解し、 軽減するために開発された一つの技法」 であるとし、 図1に示すように、 実施する際に必要とされる、 目的と調査範囲の設定、 インベントリ分析、 環境影響評価、 結果の解釈という4つのステップが明確にされた2)。 この一般原則に則って、 ライフサイクルインベントリに関する規格(ISO-14041)が1998年10月に発行され、 さらに、 環境影響評価の規格(ISO-14042)、 解釈の規格(ISO-14043)が2000年春に発行される予定となっている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インベントリ分析は、 LCA実施の目的に合致するように設定された調査の範囲に含まれる各プロセスでの資源の消費量や環境への排出物量を計算するステップである。 インベントリ分析を実施する際には、 まず対象とする製品の製造・使用・廃棄に係わるデータの収集が必要である。 これらのデータは、 一般に 「フォアグランドデータ」 と呼ばれる。 対象とする製品に直接関与するデータである。 次に、 製品に使用される素材の製造や、 使用段階で消費される電気を発電する時の排出物量などのデータなどが必要となる。 これらは一般に 「バックグランドデータ」 と呼ばれる。 対象とする製品に間接的に関与するデータである。 この両者の関係を冷蔵庫を例に図2に示す。 フォアグランドデータは、 LCAの実施者が自己の責任で収集しなければならない。 対象とする製品に直接関与するデータなので、 実施者でなければデータ収集ができず、 換言すれば、 実施者によって収集可能なデータである。 一方、 バックグランドデータは、 対象とする製品に直接関与していないので、 LCAの実施者は収集困難であり、 文献やLCAの実施例から引用しなければならないことが多い。 素材の製造データなどを文献から得ようとすると、 文献ごとに (素材ごとに) 使用している電気の製造や重油の燃焼による排出物量などのデータが異なることが多いので、 データの整合性に注意する必要がある。 LCIでは対象とする製品またはサービスに係わる膨大なデータを扱うので、 計算用のソフトウェアが必要である。 我が国でも、 東芝エンジニアリング3)、 日本電気4)、 日立製作所5)がLCA用のソフトウェアを市販している。 資源環境技術総合研究所でもLCA用ソフトウェア 「NIRE-LCA」 を開発し6)、 1995年以来2000年1月までに約250件の技術指導を実施して来た。 その成果を踏まえ、 「NIRE-LCA.ver.3」 を開発した7)。
図3の計算には、 多くの仮定が含まれ、 完全なライフサイクルインベントリ分析とは言えない。 しかし、 この図から冷蔵庫のライフサイクルでの二酸化炭素排出の大まかな傾向を知ることができる。 たとえば、 冷蔵庫の一生で二酸化炭素が最も大量に排出されるのは、 冷蔵庫を使用する時に消費される電気を供給するために必要となる発電所からの排出である。 これが冷蔵庫の一生における二酸化炭素排出量の約95%を占める。 したがって、 今後、 二酸化炭素の排出量を少なくするためには、 冷蔵庫の電力消費を小さくすることが必要である。 同時に、 冷蔵庫に使用される素材の製造が原因となる二酸化炭素の排出量は、 冷蔵庫のライフサイクル全体では4%弱であることがわかる。 この内訳を材料別に示したグラフが図4である。 冷蔵庫には鉄板とプラスチックが多く使用されているので、 それらの製造に起因する二酸化炭素の排出量が、 素材全体を製造する時に排出される二酸化炭素の量の約87%を占める。 製品である冷蔵庫を出荷する時に梱包材として使用されるダンボールを製造する時に排出される二酸化炭素の量もかなり多い。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1−3) 環境影響評価
分類化では、 資源消費や排出物を予想される環境影響の種類 (影響カテゴリ) に振り分ける。 たとえば、 「地球温暖化」 という環境カテゴリには、 二酸化炭素やメタンなど地球温暖化に関係する物質が振り分けられる。 次に、 二酸化炭素とメタンでは、 同じ1キログラムでも地球温暖化への寄与が異なるので、 メタンの排出量と二酸化炭素の排出量を単純に足し算するのではなく、 それぞれの地球温暖化に対する寄与率をかけた上で、 加えることになる。 これが特性化である。 地球温暖化については 「地球温暖化に対する政府間パネル (通称IPCC)」 という科学者の国際協力機関により、 さまざまな物質の寄与率が推定されているので、 これを用いて地球温暖化への影響をまとめることが行われている。 その概略を地球温暖化とオゾン層の破壊を例にとって図5に示す。 表2にLCAを世界的にリードする学会である欧州のSETAC(Society of Environmental Toxicology and Chemistry:環境毒物化学会)で指定されている環境影響カテゴリを示す9)。 LCAでは、 表2のように多くの環境カテゴリについて考えることが必要とされているが、 実際には、 まだ研究中の環境カテゴリが多い。 統合評価では、 環境カテゴリのうちどれが重要であるか判断し、 総合的に評価する。 現在、 世界各地のLCA研究機関で統合評価の手法が研究されている。 たとえば、 1995年の秋に、 各素材の製造工程での排出物の環境影響を総合評価し、 素材のインディケータとして示す 「エコインディケータ95」 と名付けられた手法が提案された10)。 これは、 カテゴリごとの評価を、 ヨーロッパ全域でのダメージを削減する目標値を基準に重み付けする手法である。 その概念を図6に示す。 エコインディケータ95では、 資源やエネルギーの消費が考慮されないこと、 不確実性が大きく科学的に十分判断できないことに対して目標値を設定しなければならないことなどの問題がある。 しかし、 後述するように新製品の設計のために素材を選択するような時には、 素材ごとの 「環境へのやさしさ」 がインディケータとして決定されていると便利である。 エコインディケータ95により算定されたインディケータを用いて、 製品を評価するケーススタディが行われるようになっている。 このような統合評価手法は、 環境負荷の少ない製品購入の基準、 それを推進するためのいわゆるエコラベルなどへの応用も考えられ、 LCAを利用する今後の方向性を示している。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. タイプラベルとエコデザインDfE
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(3−1) タイプラベル LCAは本質的に、 各企業での環境負荷データの公開という側面を持っている。 組立産業である企業が製品の評価をLCAで行おうとすれば、 素材産業に環境負荷データの公開を求めることになる。 そこで、 各企業が自社製品の販売にあたり環境負荷データを製品に付与するいわゆる 「タイプ」 の環境ラベルが検討され11)、 数社の企業で試行されている12)。 このラベルの普及は消費者や官公庁でのグリーン購入の動きと対応している。 実施にあたっては、 各企業が単独でLCAを実施することが困難であること、 どのような排出物に関する負荷データを付与するか明確でないことなどの問題がある。 しかし、 各企業がデータを収集することができない上流の産業については、 その産業全体での平均値または代表値を使用するなどの対応が考えられ、 上述の業界の平均値または代表値の作成と連携して実施の方向を模索することが必要である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(3−2) エコデザイン、 DfE (Design for Environment) 現状のLCAは、 現在ある製品の評価という側面が強い。 今後は、 環境負荷の少ない製品の開発・普及に役立つツールとして発展することが期待されている。 環境負荷の少ない製品またはその開発は、エコデザイン、 DfE (Design for Environment)、環境調和型製品設計などと呼ばれる。 冒頭に述べた展示会で使われた 「エコプロダクツ」 などの用語もあり、 それらの相違が定義されていない。 ここでは同義として扱う。 1999年の6月に、 DfEの国際規格化の検討が開始された。 環境負荷の少ない製品設計を推進するためにオランダで企業の指導に使用されているチェックリストを表3に示す13)。 環境負荷の少ない材料の選択、 材料の使用量の削減、 使用中の消費エネルギーの削減などがチェックされることになっている。 これらは、 製品のライフサイクルの各段階をおおまかに考慮することを意識している。 また、 フランスのLCAコンサルタントであるエコビラン社のソフトウェアEIME (Environmental Informationand Management Explorer)では、 廃棄の段階をさらに詳細に分け、 リユース可能なパーツの割合、 リサイクル可能な材料の割合などもデザインインディケータとして採用している14)。 製品設計のチェックリスト
最初に述べたように、 LCAは、 これらのインディケータが巡り巡って環境にどのように影響を与えているかを目的に添って評価する手法である。 LCAでは、 調査の目的として対象とする環境カテゴリをまず決定し、 それに関与する排出物を特定して、 寄与が大きな工程を欠かさずに調査する。 一方、 DfEでは多様な環境影響を考慮することが期待されるので、 一般に環境影響のカテゴリを特定することができない。 したがって、 特定の排出物のみに着目することもできない。 製品のライフサイクルに関与する工程の寄与は、 排出物によって異なるので、 調査する範囲の設定も非常に困難なものとなる。 DfEに期待される多面的な環境側面の評価は、 LCA調査の範囲を限定することを困難にし、 またそのために必要な排出物などのインベントリ項目を増加させ、 データの収集を非常に困難なものとしている。 DfEでは、 多面的な環境側面の評価をしなければならないのでLCAの実施が困難であり、 LCAに代わる方法として、 材料の使用量の削減や使用段階のエネルギー消費量など製品固有の特性がチェックリストとして採用される結果になっている。 しかし、 チェックリストを用いて設計した製品の環境影響への改善度を総合的に評価するためには、 やはりLCAを用いた環境影響評価が必要となる。 たとえば、 BDI社のDFMA (Design for Manufacture and Assembly) では、 Material (材料)、 Energy (エネルギー)、 Toxicity (毒性) に着目したMET pointsを採用している15)。 また、 Wimmer16)は、 エコインディケータ95を用いた評価を試みている。 前述のEIMEでは、 LCAの手法と結合し、 各種の環境影響評価が適用できるようになっている。 現状のDfEでは、 チェックリストによる評価が先行しているが、 それは、 多種の排出物に対してLCAを実施することが困難であるからである。 DfEにLCAを直接に応用するためには、 インベントリ分析用データの充実と環境影響評価手法の研究を進展させることが必要である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. まとめ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
環境の重要性を十分に認識している消費者の増大を背景として、 「環境にやさしい」 製品開発が求められている。 製品の環境への影響をきちんと評価するためには、 LCA手法による評価が必要である。 しかし、 インベントリ分析が困難な排出物が多く、 また環境影響評価の手法も研究段階にある。 したがって、 LCAを完全に実施する困難さを回避するためにチェックリストによる製品設計が推進されている。 LCAを実施しやすいものにするために、 通産省のLCAプロジェクトが開始され、 また、 さまざまな研究機関でデータの整備、 ソフトウェアの開発、 環境影響評価手法の開発が行われている。 企業でも、 自社製品をLCAを用いて評価し、 その結果をタイプラベルとして公表する動きがある。 タイプラベルは、 企業のLCAデータの開示を急速に進める可能性を示している。 今後、 チェックリストによる製品開発にLCA手法を加え、 製品の環境への影響をきちんと評価することが広まって行くと思われる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■稲葉 敦 (いなば・あつし) 1952年生まれ。 81年東京大学大学院 (化学工学) 博士課程修了、 工学博士。 同年、 公害資源研究所 (現:資源環境技術総合研究所) 資源第1部1課研究官。 石炭液化技術開発を研究。 84〜86年米国商務省標準局火災研究所で、 高分子の熱分解反応機構について在外研究。 86〜87年工業技術院サンシャイン計画推進本部開発官付き併任。 87年4月併任解除後、 石炭の液化および石炭技術評価、 地球温暖化対策技術評価研究に従事。 90年12月〜92年4月オーストリア国際応用システム研究所で、 エネルギー需給分析およびエネルギーシステムについて在外研究。 92年4月燃料物性研究室主任研究官。 エネルギー関連技術評価研究およびライフサイクルアセスメントに関する研究に従事。 94年12月エネルギー資源部エネルギー評価研究室長。 99年11月より企画室長、 現在に至る。 専門は化学工学。 石油学会奨励賞 (92年)、 日本エネルギー学会進歩賞 (94年)、 科学技術長官賞 (研究功績賞) (98年) 受賞。 著書に 『LCA実務入門』 (丸善) (分担執筆) 等。 通産省LCAプロジェクト:運営委員会副委員長・インパクト研究会主査、 日本工業標準調査会環境情報企画専門委員会委員。 |
岐阜県産業経済研究センター
| 今号のトップ |