| 特集論文 |
| 「女性にとっての交流社会」
|
| (有)トランタンネットワーク新聞社取締役社長 藤本 裕子
|
はじめに |
|
21世紀は変革の時代だと言われている。 個性の時代、 そして価値の多様化の時代へと、 社会は新しいライフスタイルを甘受し、 新時代の幕を開けようとしている。 しかし、 実際にそれは一部の女性たちのライフステージの中で提唱されただけで、 生活の現場にいる女性、 特に子育て中の母親たちには届いていないのが現状である。 それは、 少子化が今日の大きな社会問題になっているという事実を見れば明確である。 2000年に入り、 失業率は過去最悪の数字を記録し、 リストラ、 不況の波は一般家庭にまで押し寄せてきた。 社会経済学者のP・Fドラッカーは、 この不況社会をどうしたらいいかという質問に、 「It's not recession. It's transition.」 と答えたという。 これは不況ではなく、 転換期であると。 つまり不況対策を講じるより、 新しい時代への身繕い、 準備をすべき時だというコメントだ。 さて、 「女性にとっての交流社会」 というテーマで論じるにあたり、 私が発信すべきことは何か。 トランタンネットワーク新聞社 (※) の代表として、 1989年から今日まで多くの女性たちと交流してきた中で得た情報、 さらにその経験と実績を考察しながら、 このテーマについて論じたい。 単なる机上の空論ではなく、 生活の現場にいるからこそできる提案を。
※トランタンネットワーク新聞社とは |
少子化の今、 子育ての現場では |
|
日本社会は今、 急速な人口構造の変化に直面している。 1970年代頃から加速した高齢化は他の先進諸国にも類を見ないほど早く、 2020年頃には、 高齢化率 (65歳以上人口の比率) が27%を超えるという脅威の数字は、 社会経済的にも重大な問題を抱えている。 また、 その高齢化と表裏一体の関係にある、 少子化問題。 1950年頃には4.3ほどもあった日本の合計特殊出生率が、 2000年に入り1.34にまで落ち込んだ。 少子化が社会に及ぼす影響に、 誰もが危機感を持っている。 なぜ出生率が低下するのかというと、 その大きな原因は晩婚化にあると言えるが、 いわゆる完結出生力 (既婚者が生涯に産む数) には大きな変化は認められない。 つまり、 結婚して子どもを産むことに変わりはないが、 結婚年齢が高くなったことで出生率そのものを低下させた。 理由は女性の高学歴化である。 女性の就業機会の拡大は、 結果として、 女性に経済的自立を実現させ、 結婚を遅らせることになったのである。 こういう社会情勢の中で、 今、 社会に新しい流れが起こっている。 価値の多様化の時代と言われ、 女性のライフスタイルは近年大きく変化してきたとは言え、 それはまだ一部の女性に限られている。 確かに、 女性の高学歴化は、 女性の社会的地位の高まりにつながったという事実はあるが、 専業主婦の社会的地位は旧態依然。 未だ、 その評価は低い。 いわゆる高度経済成長期の、 「父親はソト (仕事)、 母親はウチ (家庭)」 という性別役割分業による弊害が根強く残っているばかりか、 今日では、 「父親はソト、 母親はウチとソト」 という、 新性別役割分業になった。 つまり、 女性には家事、 育児 (無収入労働) の他に、 仕事 (収入労働) という二重の責務が課せられた。 主婦の負担はますます重くなったのである。 このように、 働く女性、 特に仕事を持つ母親の置かれた環境の劣悪さが、 少子化問題に大きな影響を及ぼしていることに気づいた人々は、 ようやく今それを口にし、 社会全体が模索し始めた。 しかしながら、 子育ての環境はある意味で働く女性だけでなく、 むしろ家庭の中で家事、 育児をしている専業主婦の方が深刻だと言える。 昨年起こった音羽事件では、 マスコミが母親の問題をクローズアップしたことによって、 子育て環境の悪さを多くの人が意識し始めた。 こうした流れを踏まえ、 少子化対策としての子育て支援が全国各地で一種のブームになっていることは決してマイナスではないが、 今度は、 その支援の在り方が問題になってくる。 子育て支援の恩恵を直接被っているのは、 子育ての現場にいる母親たちではない。 同じように高齢化社会に入り、 猫も杓子も介護ビジネスへの参入に躍起になっている現状を知れば一目瞭然。 社会貢献という言葉を武器に、 あちこちで業者が誕生している。 制度が変わっても、 変わらないのは社会を構成している人々の意識。 子育てが次世代をつくる社会的事業だということについて、 母親も社会も認識が足りない。 子どもをどういう価値観で育てるかが将来の社会をつくる基礎になるのである。 つまり、 大切なことは、 母親自身の子育てへの誇り、 さらには子育ての社会化であると言える。 |
女性のライフスタイルと交流 〜サークルからネットワークへ |
|
ここでは、 サークルの源流は割愛して、 近年のいわゆる 「女性の時代」 におけるサークル及び、 ネットワークについて論じる。 サークルとは、 ある個人の欲求の充足を目的としていると広義に解釈する。 つまり、 人との交流からさまざまな情報を得ることで、 個人の生活に潤いを与えるということ。 サークルはそれぞれに多様な契機を持ち、 それは時間の経過とともに性格をも変えていくという順応性もあり、 それが女性の特質とフイットしている。 昨今のサークル活動の背景には、 70年代のウーマンリブから始まり、 フェミニズムが多様化して成熟期に入った90年代といった女性運動のシナジー効果があることは否定しない。 だが、 そこには属さないサイレントマジョリティの女性たちに、 交流の機会を与えたのは、 婦人会、 PTA、 町内会、 子ども会といった地域活動である。 しかし、 これらの活動状況を見ると、 未だにヒエラルキーが存在し、 そこに所属する女性たちの多くが一種のノルマを課せられているのだ。 そんな中で自然発生的に誕生したのが 「子育てサークル」 であり、 「趣味のサークル」 なのである。 「子育てサークル」 はよく、 母親たちの社会参加の一歩であると言われている。 確かに核家族化と地域社会の喪失によって、 母親たちは、 子育ての情報交換する場、 人とふれあう機会を失った。 そんな状況下にあって、 自然発生的に生まれたサークルもあれば、 行政支援の一環として誕生したサークルもある。 前者は、 いわゆる主婦の井戸端会議や幼稚園ママの遊び仲間が多く、 後者は保健所の母親学級や地域の生涯学習支援係が募集したセミナー等から、 そのまま行政管理下のサークルへとつながったもの等。 こうして全国に何千何万というサークルが誕生した。 ここでもう一つ忘れてならないのは、 こうしたサークルは、 子育て中の母親たち (専業主婦) にとって、 貴重なアイデンティティ確立の場になっているということである。 |
サークルの種類 |
|
一口にサークルと言っても、 親子のふれあいのサークルからNPOや有限会社のように法人化するサークルもあって、 その活動の多種多様性に驚かされる。 あえてセグメント化するならば、 以下の図1の通り大きく3形態に分けることができる。 |
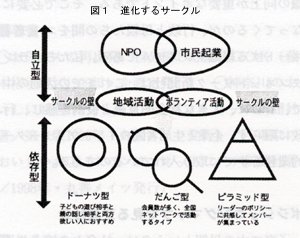 ■地元密着・親子でエンジョイ (ドーナツ型)
■地元密着・親子でエンジョイ (ドーナツ型)子どもの遊び相手が欲しいという母親が運営するサークル。 メンバーは0歳から未就園児の子どもと母親が中心。 子どもは元気に遊び、 母親は仲良くおしゃべりといった、 和気あいあいの雰囲気。 公民館や公園で活動し、 手作り行事も楽しんでいる。 保健所主導の子育てサークル等もこのタイプ。
■地域活動・母親パワー (だんご型)
■社会発信・テーマ追及 (ピラミッド型) |
行政支援の問題点と今後の展開 |
|
少子化対策として行政が積極的に行っている子育て支援の一つに、 サークル支援がある。 これは、 行政が地域の母親に資金的、 あるいは物質的な提供をして、 母親たちにサークルを作らせ、 さまざまな活動を支援している。 だが、 行政主体のサークルは、 どれも金太郎飴状態。 母親たちにやりたいことがあっても、 多くの規制に縛られ自由がきかない。 また、 助成も単年度にとどまり、 翌年からは助成されないため、 活動できずに解散に至るサークルも多いのが現状だ。 本来、 生活者に求められるサービスを提供するのが行政の役割だが、 管理範囲内に収まらないサークルの支援は有り得ない。 それならば母親サークルも、 行政支援を賢く利用すればいい。 失敗の許されない行政なのだから、 口を出すのは当然であり、 両者に今、 必要なのは対等なパートナーシップである。 母親たちも、 行政の体質を変えていくくらいの意気込みを持ちたいものである。 活動や企画に失敗が許されないこと自体ナンセンスだが、 失敗か成功かの分岐点は実に明解。 ここだけは困るというポイントさえ押さえれば、 後は簡単。 要は表現方法なのである。 つまり、 プレゼンテーションである。 今後、 地方分権制度により、 自治体の責任体制はさらに強化されるであろうことを考えると、 母親サイドの意識の向上が重要なポイントである。 そこで必要になってくるのが、 行政と母親たちの間をコーディネートする組織やシステムである。 私たちトランタンネットワーク新聞社は、 これまでの活動の中で、 ここに、 大きな社会的意義と役割を感じ、 行政に限らず、 企業と生活者間のインタプリテーター的業務をすでに取り入れているのである。 |
ポジショニングマップで見る交流社会 |
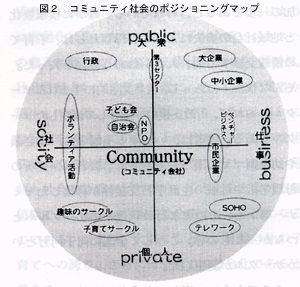 子育て中の母親というのは、 社会との接点が遠くなりがちである。
子育て中の母親というのは、 社会との接点が遠くなりがちである。 そこで、 社会の中で自分は今、 どのポジションにいるのかを認識することが大切になってくる。 これまでの生活の拠点は、 「自宅」 と 「公園」 と 「スーパー」 というトライアングル地帯に限定されていた母親が、 社会全体を俯瞰して見ることで、 自分の置かれている社会的なポジションを明確にすることができるようになるのである。 図2の個人的な活動から社会的な活動へ、 そして、 社会的活動からビジネスへ等、 活動の移行形態がわかる。 母親たちはサークル活動や地域活動など、 さまざまな人々との交流により、 意識を持ち始める。 単なるボランティアから自立型の地域活動への移行こそ、 21世紀のコミュニティ構想の第一歩なのである。 |
交流からコラボレーションへ |
|
情報化社会の今、 交流もさまざまな形態が可能になった。 特にインターネットの普及により、 グローバル&地域分散型のネットワーク構築が可能になり、 情報インフラが整備されるに至った。 SOHO、 テレワークなど、 「個」 を主体とするワークスタイルは、 市民権を得て発展し続けている。 これにより、 世代格差もなくなり、 誰もが平等にチャンスを得ることができるようになった。 また、 労働市場の多様化は、 子育て中の母親にも働き方の選択肢を与える結果となった。 時代の趨勢は、 ネット上で交流するデジタルコミュニティの出現へと大きく傾いている。 一方、 政治では中央集権から地方分権へと大きな変革を迎え、 今や、 「地域」 の時代。 成熟した社会では、 モノからヒト、 あるいは情報の時代へ移行し、 人々は人間らしく生きる場を求め始めている。 一気に突入する高齢化社会がそれを助長しているのも事実である。 マズローの法則 「人間の最終欲求は自己実現である」 を誰もが否定しない社会になった。 そんな時代に必要なもの。 それは、 個人の知恵、 知識、 ノウハウである。 これらを最高の資源として勝負する。 そして出た結果、 一人ひとりの個性や能力を積極的に評価し、 相応なインセンティブ (報酬) を与えていく、 そんな社会システムが必要となっている。 トランタンネットワーク新聞社の 「ブラボー子育て21・家庭保育園」 のコンセプトが、 保育士の資格より、 子育ての経験や知恵を重視しているのは、 正にここにある。 さて21世紀は、 男女を問わず、 ライフスタイルに合った働き方を選択できる時代である。 そして、 それを実現するために問われるのは、 個人の能力である。 情報化社会の今、 人々は溢れる情報に混乱している。 しかし、 本来、 情報の発信者は 「人」 であるということを忘れてはならない。 つまり、 人は人と出会い、 さまざまな交流をしながら情報を得る。 さらに情報と経験を蓄積する中で、 何かを創り出す能力を発揮する。 例えば、 企画力、 コミュニケーション力、 マネジメント力、 創造力、 交渉力といった 『生きる力』 を身に付ける。 すなわち、 21世紀は交流からコラボレーション (共創) の時代なのである。 社会は大企業 (集団) から個の時代へと変化しつつある。 ベンチャービジネスやNPOなど新しい動きの一方で、 生活者たちは地域に役立つ事業に取り組み始めている。 まだまだ全体から見ると少数ではあるが、 小さな経済効果をもたらすコミュニティビジネスが各地で起こり、 活発化しつつある。 厚生白書では、 子育てに夢が持てない社会と定義されたが、 21世紀を 「夢をカタチにする」 時代にするために、 男女格差をなくし、 世代を超え、 すべての人が社会の中にいる自分のポジショニングを意識しながら、 共に社会を創っていく。 さらに、 こうした新しい社会のしくみや産業構造の変化を真摯に受け止め、 情報として伝えることが肝要である。 昨年制定された、 男女共同参画社会法も、 会社だけではなく、 生活の現場で生かされてこそ意味がある。 ライフスタイルや価値観の変化は 「地域」 に新たな変革をもたらすだろう。 P・Fドラッカーが示唆した通り、 今こそが、 絶好のチャンスなのだ。 最後に、 現在子育てをしている母親たち、 そして将来母親になるであろう、 すべての女性、 そして社会に伝えたい。 今こそ、 「支援されるお母さんからアクションするお母さんへ」。 21世紀の夢の実現は、 私たち一人ひとりのアクションにかかっている。 |
トランタンネットワーク新聞社の活動内容 |
|
■発行物 ◯月刊 お母さん業界新聞 (5万部) ◯トランタン新聞 (5000部) ◯イヴイヴ (3000部) ◯トランタン新聞関西 (3000部) ◯トランタン新聞九州 (3000部)
■著書
■メインイベント
■ブラボー子育て21プロジェクト
■家庭保育園
■お母さんのたまり場・BRAVO!情報ステーション
■新資格制度
■トランタンネットワーク新聞社ホームページ (お母さんのテーマパーク・ブラボーワールド
■連絡先 |
岐阜県産業経済研究センター
| 今号のトップ |