| 研究中間報告 |
| 「高齢・成熟社会における交流および 交流産業のあり方に関する総合調査」 中間報告要旨
|
| (財)岐阜県産業経済研究センター主任研究員 椛島 康記
|
はじめに |
|
(財) 岐阜県産業経済研究センターでは、 平成11年度、 12年度の2ヵ年で調査研究 「高齢・成熟社会における交流及び交流産業のあり方に関する総合調査」 を、 (株) 三菱総合研究所と共同で行っており、 平成11年度は中間報告を取りまとめたので、 その要旨を報告する。 本調査は、 少子高齢化、 通信革命の進展、 グローバリゼーション、 モノから心へといった高齢・成熟社会が実現する中で、 人々の生活、 仕事等のライフスタイルがどのように変化し、 その中で 「交流」 にどのような役割が期待されるのか (交流の需要側)。 それにもまして産業 (供給側) がどう関わっていけるのかを検討することを目的としている。 11年度においては、 高齢化、 情報化等経済・社会の変化の把握を行い、 その上で、 人々の新しいライフスタイルを予測し、 それを支援する新しい交流産業の定義・検討フレームの提示を行った。 そして12年度は、 具体的に新しい交流産業のあり方、 さらには岐阜県にふさわしい交流産業のあり方を導出する。 |
1.高齢化、 情報化等によってもたらされる 経済・社会の変化 |
|
少子高齢化等による経済・社会への様々なマイナス作用が懸念されているが、 見方を変えれば、 真に豊かで暮らしやすい社会の創造へ向かう転機とも考えられ、 以下にその主要な変化の概要を述べる。 |
1-1 少子高齢化による経済・社会の変化 |
|
(1) 生産年齢人口と老年人口 生産年齢人口 (15歳から64歳まで) は、 すでに95年をピークに減少傾向にある中で、 老年人口 (65歳以上) は増加傾向にあり、 21世紀初頭には4人に1人、 中頃には約3人に1人となると予測されている。 このような中で、 高齢者を一括りにするのではなく、 75歳まで (ヤング・オールド) とそれ以上 (オールド・オールド) に分けて考えることが必要であり、 例えば前者には活動・就労の場を与え、 後者には地域ケアを充実させる等の施策が求められる。 また、 2010年には、 平均世帯人数は3人をきると見られ、 その中でも特に高齢者間の収入・資産格差が拡大する中で、 高齢者単独世帯の低迷が問題となり、 様々なケアが必要となる。
(2) シルバーサービス産業
(3) 土地の有効活用等
(4) 産業構造・就業構造の変化
(5) 教育 |
1-2 情報化による経済・社会の変化 |
|
自らの目的を明確に意識した人々の、 インターネットを通じた新しい結びつきが生まれる。 その結びつきとは、 地域コミュニティとは異なる、 離脱が自由な緩やかなコミュニティである。 ワークスタイルへの影響としては、 裁量労働制やテレワークがもたらす効果として、 これまで家事に拘束されていた女性や物理的移動が容易でない高齢者や障害者の雇用を大幅に拡大する可能性がある。 一方、 情報化によるペーパーワークの効率化は、 ホワイトカラーの生産性を向上させ、 ひいては必要とされるホワイトカラーの数を減少させることが可能となり、 これらの人々を真に身体的技術が必要とされる生産活動や福祉などへ振り向けることができるようになる。 但し、 これには政策的雇用調整が必要であり、 例えば育児や医療・介護といった分野においては、 利用者が良質なサービスを求めていることを踏まえ、 民間事業者を活用すること、 そのための有料職業紹介事業や労働者派遣事業に対する規制緩和や職業能力開発・評価事業を公的に支援することが求められる。 さらには、 アメリカ等と比較して、 割高な通信コストの低減も、 もちろん求められる。 |
1-3 高学歴化による経済・社会の変化 |
|
とりわけ、 中高年、 女性の高学歴化が進展する。 1990年の55~65歳の女性人口の内、 大卒者の割合は6%に過ぎなかったが、 2010年には22%に高まることもあり、 新しいライフスタイルの誕生が予期される。 すなわち、 行動的で消費意欲も旺盛、 自分の楽しみや自分を磨くことに関心を持ち、 若い頃から慣れ親しんだ車やロックに熱中し、 パソコンや電子メールを駆使するといった新たなタイプの高齢者が登場すると考えられる。 また、 (株) 住友生命総合研究所の 「大都市サラリーマンOBの社会参加活動に関する研究」 によると、 学歴が高くサラリーマンとしての勤続年数が長い高齢者ほど、 地域コミュニティに依存するよりも、 むしろ自身の趣味に余暇時間を投入する傾向にあるということが言われている。 |
1-4 消費市場における変化 |
|
(1) 新商品需要の減少 新しいモノ好きの若い世代 (女子高生、 OL等) が減少するため、 新商品需要は大きく減少すると見られる。 しかし、 その中で団塊ジュニア世代が注目される。 この世代は、 出生人口が200万人の大台に乗った1971年から74年に生まれた人々を中心とする世代で、 2000年には20代後半に入り、 親元を離れて独立したり、 結婚したりという、 人生の第二ステージを迎えており、 それに伴って第二ステージ特有の消費が発生すると考えられる。 また、 彼等には自分が主人公という生き方を当然の事とし、 好きな事には投資を惜しまないという特性 (マイイズム) もあり、 このようなライフスタイルは、 今の時代とシンクロし、 上下の世代に影響を及ぼしている。 団塊ジュニアのライフスタイルは、 以下のような特徴を持ち、 モノ本来の機能にこだわった家電、 デザイン性に優れたインテリアや生活雑貨、 独立志向と資格取得、 パーソナルな情報機器やニア・ウォーターの需要増に至っている。
①等身大の暮らし (余分なものはいらない)
(2) 耐久消費財市場の縮小と変貌 |
1-5 循環型リサイクル社会に向けて |
|
高度経済成長時代は、 経済発展と引き換えに環境破壊が進んだ時代でもあった。 今日、 環境破壊は地球規模の問題となり、 生活者一人一人に、 大量消費・大量廃棄型ライフスタイルの見直しを迫っている。 さらに、 産業間・企業間の連携や都市環境整備においても、 循環型の発想 (配送の相互乗入れや共通パレットの利用、 企業とその廃物利用業者との連携等) が求められており、 それらに対する国や地方自治体の支援が必要である。 |
1-6 グローバル規模の交流の拡大 |
|
ITの発達により、 「情報の世界同時共有」 が進行した。 すなわち情報はあらゆる分野に発信され、 ヒトは豊富に流れ込む情報の中から取捨選択し、 フィードバックすることとなる。 魅力ある情報にはフィードバックが多く、 このフィードバックの多さ自体も情報として共有されることにより、 特定分野への情報蓄積が始まる。 すなわち魅力あるプロジェクトやベンチャー企業は世界中から多くの投資家の関心を集め、 株価は上昇し、 成功のチャンスがより拡大することになる。 |
1-7 人々の意識の変化 |
|
社会と人々の意識の変化を、 特に人口ボリュームの大きい団塊世代と団塊ジュニア世代を比較しながら見ると、 親子では微妙にニュアンスが異なっているものの、 同質化傾向が見られる。 このように、 これからのライフスタイルは、 年代の差というよりも、 個々人の価値観の差を反映するものとなり、 似たような価値観・ライフスタイルを共有する人々が、 緩やかな連携を結ぶと思われる。 それゆえ創造性の高い、 豊かな社会の形成のためには、 異なる価値観を有する人々との交流が大きな意味を持つものと考えられる。 |
2. 新しいライフスタイルの創造 |
|
以下に新しいライフスタイルの創造における社会・政策的な課題を検討する。 |
2-1 ヤング・オールドの発掘と活用 |
|
団塊の世代が高齢化することにより、 高齢化は急速に進展する。 現在の高齢者は、 高度経済成長期の地価上昇や高金利の恩恵を受け、 十分な資産の蓄積ができた世代である。 しかし、 これからの高齢者は、 年功序列賃金で若い時は安い賃金で働き、 これからその分を退職金等で取り替えそうという時に、 早期退職優遇制度の導入など、 定年までの雇用問題が持ち上がっている。 さらに、 老後の収入源である年金についても、 支給開始年齢の引き上げ等により、 雇用や老後所得の不確実性が高まっている。 一方、 早期退職優遇制度等の活用により、 将来のヤング・オールドがUJIターンして、 自然豊かな農山村での第一次産業やペンション経営等に就労する動きも一部には見られるが、 これには無論、 ネットワークや中心市街地への交通システムの整備等、 農山村といえども、 物理的・情報アクセス的に孤立しないという環境下にあるという前提があってこそのライフスタイルである。 |
|
(1) 定年延長と新しい賃金体系 高齢者、 特にヤング・オールドの雇用 (定年延長や再雇用) を考える際、 重要な事は、 中高年のリストラと違い、 子育てが終わっていたり、 住宅ローンを完済していたり、 あるいは年金をもらっていたりと、 賃金面での譲歩はしやすいと思われる。 さらに、 ワープロやパソコンの普及は、 記憶や単純計算等、 高齢者が衰えがちな能力を補うとともに、 判断力や知恵といった、 むしろ高齢になればなるほど、 身につく能力を有効に活用させることにもつながるものと思われ、 このため、 今後は高齢者のニーズに応じたソフト開発等への高齢者の参画も期待される。 また、 昔のように何年もかかって熟練するという仕事が減ったことも、 今までとは違う仕事に新たに就くという際の高齢者雇用を考える場合には、 よい傾向となると思われる。 一方、 総務庁の 「高齢者の生活と意識に関する国際比較調査」 (平成7年度) によると、 高齢者の就業意欲は決して低くはない。 このため、 高齢者の働く場の整備が求められ、 場合によっては、 それが生き甲斐となるかもしれない。 さらに、 全部とは言わないまでも、 少子化による労働力不足をカバーすることも期待される。
(2) 高齢者と地域社会の断絶
|
2-2 働く女性への支援 |
|
女性の労働参加の拡大要因としては、 女性の高学歴化の進展や、 それに伴って女性を必要な戦力として考えるようになった企業側の需要、 さらには少子化等の影響が考えられる。 一方、 通信技術の進歩により、 フレックス・プレイスやサテライト・オフィスで、 裁量労働制やフレックスワーク制度を活用しての就労やSOHO、 ベンチャー・ビジネス等女性の起業も多くなっている。 また、 今後はワークシェアリングが、 大企業等でも検討されるべきであるし、 公的介護保険制度の導入により、 介護における公的支援の拡充も必要である。 |
2-3 新しいワークスタイル |
|
国際化や情報化などの技術革新により就業形態は変化してきている。 今後は、 会社に貢献するとともに、 自己のキャリアを磨き、 同時に給与を得る働き方が主流となる。 貸し借りのない世界では、 自己の賃金は、 年功が重視されることなく、 常に市場賃金であるため、 「展職」 (将来に対して前向きな、 発展性のある転職) も自由であり、 失業が賃金の大幅な低下を意味することもない。 一方、 雇用は流動化し、 それが高まることにより、 仕事重視か、 余暇重視かという、 ライフスタイルに応じた組合せを追求することができるようになる。 これにより、 中高年に比べた若者の、 男性に比べた女性の、 ジェネラリストに比べたスペシャリストの相対価格が上昇することで、 フレックスワーク、 テレワーク、 サテライト・オフィス、 SOHO等の増加が予測される。 さらに、 ベンチャー・ビジネスや地域密着の住民主体のスモールビジネスであるコミュニティ・ビジネスの普及も期待されるが、 これらには自治体の独立開業支援等、 起業環境を整備することも必要である。 |
3. 新しい交流産業の定義 |
|
最後に、 人々のライフスタイルの変容に対応した新しい交流産業検討のための枠組みを考察する。 人々のライフスタイルや社会の変化の特徴をまとめると、 図1の通りである。 サテライトオフィスやSOHOの普及により、 職住近接が可能となり、 都市への人口集中は弱まり、 地方固有の価値が見直される。 これにより、 地方においては、 その地方固有の伝統文化を再発見し、 それを新しい交流産業に昇華させることが重要になる。 また、 通勤時間にとられていた時間とエネルギーを自分の趣味にまわすことができ、 オフ・タイムを充実させることが課題となることから、 オフ・タイムの充実に貢献できる交流産業の発展が重要となる。 例えば、 物質的な飽和社会にあって、 時間を有意義に使いながら楽しんで、 他に絶対ないものを生み出す、 「自分だけのモノづくり」 体験が重視されるようになり、 岐阜県の多治見にて、 自分だけの、 世界に1つしかない美濃焼を作るという行為自体も、 1つの交流形態の新しい形となるのではないだろうか。 このように、 人々のライフスタイルを表すキーワードは 「自己充足」 であり、 あるべき自分をいかに表現するか、 すなわち、 自分にしかできない生き生きとした人生を具現することを求めることである。 ここでのキーワードは 「適材適所」 であり、 人々が自身の能力を十分に発揮し、 それが他の人々にいい影響を及ぼす、 あるいは役に立つというコミュニケーションの場が必要とされている。 そして、 このような交流形態を支援する産業として、 様々な交流支援ビジネスが考えられる。 |
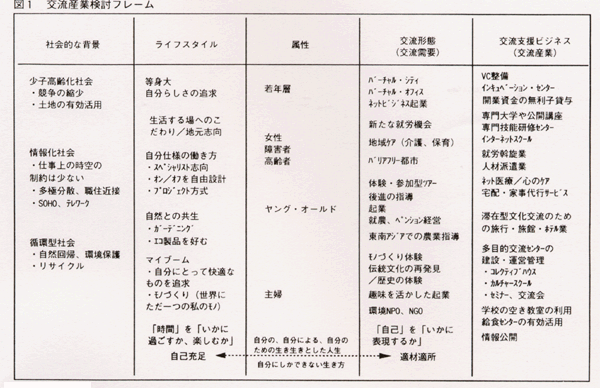 |
おわりに |
|
人々の行動やライフスタイルを、 年齢・所得等従来の物差のみで測ることは、 今や不可能となってきている。 言わば社会的な背景と実現したいライフスタイルが、 その人の属性を通して出現するのであり、 その結果、 様々な交流形態が生じ、 それに対応した交流支援ビジネスが検討され得ると考えられる。 例えば、 自然との共生に関心のあるヤング・オールドは、 余ってきた土地を有効活用し、 自分らしく就農 (定年帰農) やペンション経営を模索することも考えられる。 その際、 求められるのは、 専門大学等での教育や開業資金、 同じ志を持つ人々との交流会等への支援・サービスであり、 あるいは人材派遣業に派遣社員を要請することや、 心のケアが必要となる局面もあるのかもしれない。 これら交流支援ビジネスに関する具体的な考察は12年度に行う予定である。 |
| |
岐阜県産業経済研究センター
| 今号のトップ |