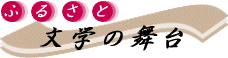
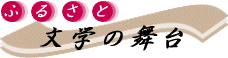
 安房トンネル (写真提供 岐阜県広報センター) |
篠原無然は、兵庫県人で、本名を禄次という。苦学して早稲田大学に学び、大正三年十一月、上宝小の代用教員として赴任、さらに辺地へとの希望を出し、平湯分校にやってきた。平湯では子供たちばかりか、青年や地区の人たちを巻き込んでの活動を展開した。今でいう社会教育のハシリであった。二年ほどの間に、地区の住民のほとんどが、交代で彼が主催する夜学へ通うようになった。一方で彼は、自己を高めるための修行なども進めた。 この活動の輪が高山方面へも、広がった。高山の青年たちが招いたのが、きっかけだった。やがて無然の足跡は飛騨全土に及ぶようになった。同八年、社会教育に専念するため教職を退き、平湯に「やわらぎのその」を設立、ここを拠点に活動を続けた。このころになると、飛騨はもちろん美濃や信州の製糸工場に働きに出かけている女性たちに対しても、激励と慰問を行っている。
同十二年、無然に師事していた若い女性が、大八賀川で投身自殺をした。無然の子を身籠ったためとのうわさが流れた。彼は反論しなかった。やがて飛騨を去った。
同十三年十一月、無然は安房峠を越え飛騨入りを企てた。平湯へ行くためであった。十三日は安曇村白骨温泉で泊り、翌日、雪の峠道にいどんだ。
「無然にとって、ここは自分の散歩道同然のところであった。しかし、星明りもない雪の降る暗い峠の頂上に立ったのは、初めてである。(中略)もうすぐ平湯の星が見えよう。なつかしい人々に会えるのだ。心が浮き立つけれど、一足ごとに速度が落ちはじめた。事実雪は多く、重くねばりつく。下半身の感覚が麻痺しつつあるのがよくわかるのだ。」
江夏は無然の最後を、このように描写する。彼は平湯まであと二キロという峠の中腹で意識を失った。迎えに出た青年たちの知らせで、平湯の人たちのほとんどが救助作業に参加したが、間に合わなかった。無然は三十六歳であった。
平湯では十九日、同地始まって以来という盛大な区葬を執行、彼に感謝した。さらに現在では「篠原無然記念館」や歌碑、遭難現地には記念碑が建てられ、偉大だった彼の遺徳をたたえている。
「雪の碑」の江夏は、飛騨の女性を主人公にした長篇小説「下々の女」で田村俊子賞を受賞した作者でもある。彼女が飛騨で社会教育の先駆的な業績を残した無然を再評価し、さらに彼が受けたいわれなきひぼうをぬぐおうとして執筆したのが、この長篇小説である。それだけに読みごたえのある内容となっている。
二十余年前、県郷土資料研究協議会(事務局・県立図書館)が、江夏を講演に招いたことがある。演壇に立った彼女は、当時執筆のため調査を進めていた無然について語りはじめた。後半になって突然、話がと切れた。事実無根のうわさにじっと耐えていた彼の心境を思ったとたん感情が高ぶり、絶句したのだった。やがてハンカチで目頭を押え、話を続けた。これには聴集の一人であった私も感激した。私にとり母に次いで、二度目の出来ごとだったからである。
私の母は高山市三福寺の出身。乙女のころ兄と一緒に城山公園・正雲寺などで開かれた無然の講習に、よく参加したという。「兄と連名で無然先生に手紙を出したところ、長い巻き紙の返事をもらい大喜びをした」ほど、無然に心服していた。
その母に私は、無然のことで自殺した女性の話はほんとうか───と質問したことがあ
る。「お身(お前)まで、そんなバカなことを信じているのか。あれは先生の活動を心よく思わなかった人たちの作り話で、先生には申し訳ないこっちゃった」と最後は涙声になり、しばらく顔を伏せていた。あんな母の厳しい表情を見たのは、それまでなかった。
老後の母は、針仕事をしながら無然に習ったという「飛騨の血のいろ」を、よく口ずさんでいた。この歌は彼の作詞でいろは四十七文字を頭にし、飛騨の風土や若者の心構えを読み込んだもの。講習会では必ず合唱させた。例えば「い」は
い いのちがけだよジョウダンよしやれ ほんにやるならやるように
母は言った。「無然先生も、歌のように亡くなられた」と。その歌とは
と どうせ死ぬなら飛騨高原のお花畑でねむりたや
昨年十二月六日、北アルプスをぶち抜いて中部従貫道安房トンネル(延長四・四キロ)が開通した。これによって冬期間も長野県側との通行が可能になった。飛騨にとり鉄道高山線の全通(昭和九年)に次ぐ「第二の夜明け」と、大きな期待がかけられている。無然は、それをどんな思いで眺めているだろうか。
| 今号のトップ | メインメニュー |