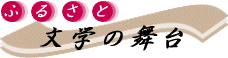
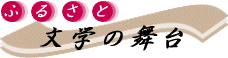
子規の歩いた道
文・道下 淳 (エッセイスト)
短歌や俳句の革新運動を進めるかたわら写生文を提唱、さらに多くの歌人・俳人を育てた正岡子規(1867〜1902)は、近代文学上重要な地位を占める人物である。彼が木曽から東濃方面を旅したことがある。地元ではほとんど忘れられているが、もっと認識する必要があろう。この旅の紀行文『かけはしの記』を読むと、当時の様子が分かり面白い。
子規が東濃を通ったのは明治24年6月末のこと。濃尾大震災発生4ヶ月前である。彼は東大国文科に在学中であったが、胸を病み喀血していた。学問を続けるか退学するかで悩んだあげく、学業を放棄して故郷の愛媛県・松山に帰った。『かけはしの記』は、そんな背景のなかで記された。
子規は東京・上野から途中まで汽車を利用、木曽路に入った。薮原宿では、『誰に贈らんとてか、われながらあやし』と弁解しつつ、名物のお六櫛を求めた。また須原宿では『名物なればと強いられて』花漬を二箱も、買わされた。この辺りは、幸田露判の小説で当時評判になった『風流仏』の舞台となったところ。『かけはしの記』には、子規の関心のほどがにじみ出ている。
木曽路では、雨に悩まされ続けた。『一重の菅笠に凌ぎかね、終に馬籠駅の一旅亭にかけこむ。夜に入れば風雨いよいよ烈しく(後略)』とある。ひどい吹き降りだったことが分かる。
翌朝、宿の娘に頼み、合羽を新調して出発した。荒町・新茶屋(長野県)から、石畳が残る十曲峠(中津川市)を経て落合宿(同市)に出たらしい。
桑の実の木曽路出づれば穂麦かな
馬籠を西へ出ると、空が広くなる。桑畑も少なくなり、麦畑が続く。美濃路に入ったのだ。彼もホッとしたのだろう。そんな気持ちが「桑の実」の句には、よく出ている。
この句に続くのが『きょうより美濃路に入る。余戸村に宿る』の短い文章である。余戸村とは今の瑞浪市釜戸・大湫両地区から出来ていた村名である。子規は馬籠を出てから余戸村まで、どの道を歩いたか不明である。彼の泊まった宿も大湫か釜戸か分からない。でも釜戸に泊まったのではないかと思われる。
 釜戸は大井宿(恵那市)の西にあり、名古屋へ行く下街道と御嵩宿(可児郡)を結ぶ中街道の分岐点である。明治中期に中街道が整備され、大湫・細久手両宿を通る上街道(中山道)より利用者が多くなった。子規はおそらく、中山道を利用、御嵩宿に出たのでなかろうか。御嵩町井尻の三差路に、「右
中街道大井宿へ達」と刻まれた明治15年建立の石の道標がある。この年号は中街道の整備終了を意味するものかも知れない。
釜戸は大井宿(恵那市)の西にあり、名古屋へ行く下街道と御嵩宿(可児郡)を結ぶ中街道の分岐点である。明治中期に中街道が整備され、大湫・細久手両宿を通る上街道(中山道)より利用者が多くなった。子規はおそらく、中山道を利用、御嵩宿に出たのでなかろうか。御嵩町井尻の三差路に、「右
中街道大井宿へ達」と刻まれた明治15年建立の石の道標がある。この年号は中街道の整備終了を意味するものかも知れない。
子規晩年の弟子である長塚節は、同38年に亡き師の足跡をたどりながら中山道を歩いている。そのときのルートが中街道だったことが、短歌の詞書からも分かる。子規の中街道通過は、まず間違いなかろう。
『御嵩を行き越えて松縄手に出づれば数日の旅のつかれ発して、歩行もものうげに覚ゆ。肩の荷をおろして枕とし、しばし木の下にやすらいて松をあるじと頼めば心地ただうとうととなりて(後略)
草枕むすぶまもなきうたたねの
ゆめおどろかす野路の夕立
この夜、伏見に足をとどむ』
松縄手とは御嵩町中か、顔戸辺りの松並木が続く直線道路を指しているのだろうか。以前地元で聞いたが、分からなかった。十返舎一九の『木曽街道膝栗毛』には、中地区に「桶縄手」という地名があったらしい記述がある。
子規は松並木の下で休んでいるうちに、須原で買った花漬を枕にうとうとした。この日歩いたのは20余キロ。健康体であれば40キロ近くは歩けようが、病身の彼には無理であった。二箱の花漬も、負担になったことだろう。その夜は伏見宿(御嵩町)に泊まった。
翌朝、早立ちをして船で木曽を下った。『かけはしの記』には川湊名は記されていないが、伏見宿から北へ約1キロのところにある新村湊からである。この湊は貨物のほか、木曽川を下る旅人たちも運んでいる。鉄道も敷設されなかった明治時代前半は、利用者が目立った。彼が乗船したとき、旅人7、8人が一緒に乗り込んだ。
すげ笠の生国名のれほととぎす
子規が新村湊で詠んだ句である。木曽川下流に出来たダムのために水位が上り、乗船場は水没したが、台地にある倉庫など一部の建物は残っていた。現在どうなっているだろうか。この新村湊に「すげ笠」の句碑を建ててもらえれば---と筆者は願っている。いつだったか地元の人たちにこのことを話したが、反響はなかった。
子規は舟で日本ラインを下り、羽島郡笠松町の対岸、愛知県・木曽川町に上り鉄道を利用西へ向かった。